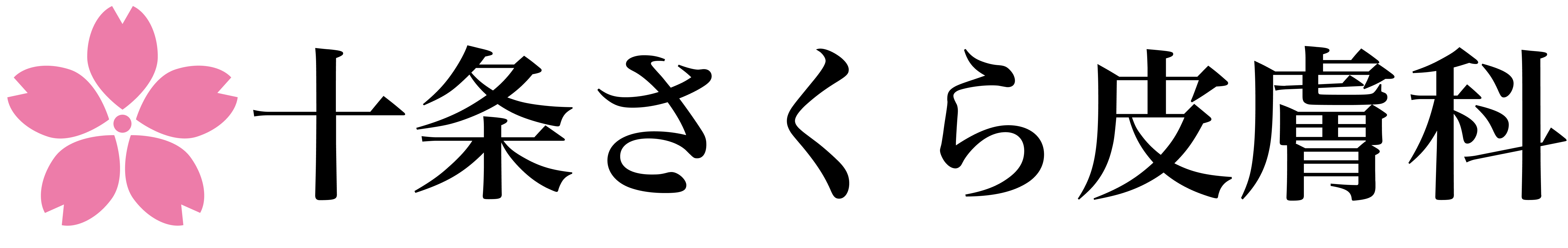一般皮膚科
Dermatology
一般皮膚科について
皮膚の病気は、日常的によくあるものから命に関わる病気までさまざまです。当院の皮膚科では、子どもから大人まで、あらゆる年代の患者様の皮膚に関するお悩みに対応しております。 湿疹、皮膚炎、じんましん、ニキビ、水虫、イボ、ヘルペス、帯状疱疹、虫刺され、乾燥肌などの一般的な皮膚疾患のほか、円形脱毛症やアトピー性皮膚炎、尋常性乾癬などの慢性疾患にも対応しております。
皮膚のトラブルにお悩みではありませんか?
皮膚は体の一番外側にあるため、常に外的刺激にさらされています。 そのため、さまざまなトラブルが起こりやすい部分でもあります。 「ちょっとした肌荒れ」や「なんとなくかゆい」といった軽い症状でも、実は重大な皮膚疾患が隠れている場合もあります。 少しでも気になる症状があれば、お早めにご相談ください。
一般皮膚科でよくある疾患
蕁麻疹(蕁麻疹)
接触皮膚炎は、刺激物やアレルゲンが皮膚に触れることで発症します。原因として、化粧品や金属、洗剤、植物などが挙げられます。 症状は、赤み、かゆみ、腫れ、水ぶくれなどで、症状が悪化すると皮膚がただれることもあります。 原因となる物質を特定し、それを避けることが治療の基本です。
湿疹
湿疹は、皮膚が炎症を起こしてかゆみや赤みが出る状態で、慢性的に繰り返すこともあります。 アレルギー体質の方や、乾燥肌の方に多く見られます。ステロイド外用薬や保湿剤を使用して治療を行います。
かぶれ(接触性皮膚炎)
蕁麻疹は、突然皮膚に赤い膨らみやかゆみが現れ、数時間で消えるのが特徴です。原因はストレスや食べ物、薬剤などさまざまです。 一方で薬疹は、薬に対するアレルギー反応で起こる皮膚症状で、早急な治療が必要です。
手荒れ(手湿疹)
手湿疹は、家事や仕事などで手をよく使う人に多く見られます。 水仕事や消毒などで皮膚のバリア機能が低下し、かゆみやひび割れなどの症状が現れます。保湿や外用薬で治療します。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、慢性的に皮膚が乾燥し、かゆみを伴う湿疹が繰り返し出現する疾患です。 遺伝的な要因や環境因子、ストレスなどが関係しており、適切なスキンケアと薬物療法が必要です。
デュピクセント注射
アトピー性皮膚炎や喘息などに使われる生物学的製剤で、炎症の原因となる物質の働きを抑え、かゆみや症状の改善をサポートします。
コレクチム軟膏
JAK(ヤヌスキナーゼ)という酵素の働きを抑え、炎症やかゆみを改善します。
モイゼルト軟膏
PDE4という酵素の働きを抑えて炎症を軽減し、かゆみや湿疹を改善します。
脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)
脂漏性皮膚炎は、皮脂の分泌が多い部分に起こる炎症性疾患です。 主に頭皮や顔、耳の周りに赤みやフケのような症状が出ます。 抗真菌薬やステロイド外用薬で治療を行います。
虫刺され
虫に刺されることで、皮膚に発疹、発赤、痛み、かゆみなどの症状が現れることがあります。虫を完全に排除することは 難しいですが、山などに外出する際は虫よけスプレーを使用し、長袖と長ズボンを着用するなど、皮膚を虫から守る対策が 大切です。発疹、発赤、痛み、かゆみなどの症状がある場合、ステロイド外用薬が効果的です。重症の場合、ステロイド内 服薬も併用することがあります。いつもと異なる発疹や痛みがありましたら、まずはご相談ください。
やけど(火傷)
やけどをした場合、速やかに患部を冷やすことが重要です。流水で約30分間冷やしてみましょう。ただし、すぐに 冷やしても赤みや痛みが残る場合、早期に治療が必要な場合があります。重度であると、水ぶくれや傷跡が残る可能性が あるため、慎重に対処しましょう。特に広範囲のやけどの場合、ショック状態に陥る可能性があるため、お早めに ご相談ください。やけどをした際に着用している衣服が脱ぎにくい場合、まず冷やした後にゆっくりと衣服を 脱がせましょう。ただし、小さなお子さんや高齢者の場合、過度な冷却による低体温に注意する必要があります。
粉瘤(アテローム)
粉瘤はアテロームとも呼ばれ、皮膚の下に袋状の組織が形成され、そこに皮脂や角質がたまり、腫瘍を形成した状態です。 通常、皮脂や角質は、皮膚表面から垢として自然に剥がれ落ちるものですが、皮膚の下の袋状の組織、および物質が少しずつ たまることで、しこりを形成していきます。袋状の組織が皮膚の下で炎症を起こすと、痛みや熱感を生じることがあり、 こうした症状を伴う場合は切開して膿を排出する必要があります。 粉瘤は、炎症や痛みが治まっても、袋状の組織を取り除かない限り再発する可能性があります。 そのため、痛みがない場合でも皮膚科を受診することをお勧めします。粉瘤の大きさや部位に応じて、手術での切除が 必要な場合、適切な医療機関をご紹介いたします。
水虫(白癬・爪白癬)
一般的に、水虫として知られる白癬(はくせん)は、真菌の一種である白癬菌が爪や皮膚表面に感染することで発症します。 白癬菌は、皮膚表面のどこにでも感染する可能性がありますが、白癬の約9割は足に発症します。特に皮膚トラブルのない 健康な方の場合、24時間以内に白癬菌を洗浄することで感染することはありませんが、人から人に感染する感染症であり、 プールや銭湯、ジムの床など、多くの人が利用する場所での感染が考えられます。白癬に感染すると、ジクジク感やかゆみが 現れることもありますが、かゆみがなく、皮膚が剥がれたり、カサカサしたりするだけの場合もあります。 当院では顕微鏡検査を行うことで、白癬菌の感染を確認できます。菌が確認された場合、抗真菌薬の外用または内服治療を 行います。外用薬に対してかぶれる方や内服薬による肝機能障害が出る方もいますので、患者様に合わせた治療を 提案していきます。爪白癬は治療期間が長引くことがありますが、根気よく治療を続けるようにしましょう。
イボ・水イボ
イボは、医学的には「尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)」といい、タコやウオノメと似た症状を示し、混同されやすい ことがありますが、実際にはヒトパピローマウイルス(HPV)による感染症になります。このウイルスはヒトに感染し、 主に手や足にイボを形成します。イボは治りにくく、時間がかかるため、根気強い治療が必要です。治療としては、 液体窒素を使用して冷凍凝固療法を行います。冷凍凝固療法では、1~2週間ごとに複数回液体窒素でイボを凍結することで、 除去していきます。ただし、この治療は痛みを伴い、血まめや水ぶくれの副作用を生じることがあります。 一方、水イボは、医学的には伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)といい、伝染性軟属腫ウイルスに感染することで、 皮膚に光沢のある白い小さなできものができます。水イボは自然に治癒する場合もありますが、引っ掻いたりすることで広がることもあります。水イボの治療方法は、自然治癒を待つか、小さなピンセットを使用して除去する形になります。お子様に対しては、麻酔のテープを使用して痛みを軽減させた上で治療を行うことも可能です。 気になるイボや水イボがある方は、一度当院までご相談ください。
口唇ヘルペス
単純ヘルペスウイルスに感染すると、唇やその周囲に小さな水ぶくれ(水疱)、発赤、ただれなどの症状が現れます。このウイルスに一度感染すると、生涯にわたって体内に潜むことになり、風邪や心身のストレスなどによって免疫が低下する度にウイルスが再活性化して口唇ヘルペスの症状が再発するようになります。初感染時には、発熱などの症状が出て重症化することもあり、再発時にはピリピリとした痛み、かゆみ、熱感が現れます。 単純ヘルペスウイルスには1型と2型の2種類があります。1型は通常、乳児期に感染し、一度感染すると生涯ウイルスが体内に潜むとされ、2型は性感染症と関連しており、性器周囲にヘルペスの皮膚症状が現れることが一般的です。 口唇ヘルペスの治療には、抗ヘルペス薬が使用されます。ヘルペスの症状が現れたら、できるだけ早く抗ウイルス薬を服用する必要があります。ヘルペスの症状が出やすい方には、発症時に内服できるよう、事前に抗ウイルス薬の処方が可能ですので、次回症状が現れた際にすぐに内服できるように薬を携帯するようにしましょう。
帯状疱疹
帯状疱疹は、水疱瘡と同様に水痘・帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる疾患です。幼少期に水疱瘡にかかったことのある人は、体内にウイルスが潜伏していますので、ストレスなどで免疫が低下したタイミングなどで帯状疱疹を発症することがあります。帯状疱疹は、神経痛のようなピリピリとした痛みのほか、次第に水疱や発赤などの皮膚症状が現れます。体の片側に広がることが多いものの、全身に広がることもあります。顔面神経麻痺や視力障害などを生じることもあるため、早期に適切な治療をする必要があります。また、発疹が消失しても、痛みが持続し、場合によっては数年にわたって続くこともあります。この症状を帯状疱疹後神経痛と呼びます。 帯状疱疹は、50歳以上で急増し、80歳までに3人に1人が発症するとされています。当院のある北区では、北区在住の50歳以上に帯状疱疹ワクチンの補助金があります。当院でも帯状疱疹ワクチン接種を行っていますので、該当する方はお気軽にご相談ください。
乾癬(かんせん)
乾癬は、皮膚が赤く盛り上がり、硬くなった角質が剥がれてポロポロとした鱗屑(粉)が発生し、硬化した皮膚がかさぶた状になる皮膚疾患です。特に、頭部、背中、肘、膝、腰、お尻、下腿などに発症し、かゆみを伴います。 乾癬には、皮膚症状以外に発熱、倦怠感、関節の痛みなどの全身症状が現れることもあります。 乾癬は、一度発症すると完治が難しく、症状が繰り返し軽快と悪化を続ける慢性疾患です。主な原因として、遺伝的要因や生活習慣などの環境要因が考えられますが、過度なストレスや緊張、感染症、薬物の刺激なども発症の要因となることがあります。症状が落ち着いても、ストレスや生活習慣の乱れなどが再発の要因になりますので、日頃からストレスをためず、規則正しい生活習慣を保つことが大切です。
尋常性白斑(じんじょうせいはくはん)
尋常性白斑は、皮膚の一部分が白く変色する疾患で、「色素異常症」に分類されます。メラノサイトと呼ばれる色素細胞の減少や消失によって引き起こされ、白斑が皮膚の一部分を完全に白く変えることもあれば、色素の減少により皮膚が薄くなることもあります。尋常性白斑は難治性の疾患とされ、発症部位によっては生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼすことがあります。原因としては、自己免疫の異常によって、自己のメラノサイトが攻撃され、色素を生成できなくなることが原因と考えられています。尋常性白斑の治療には、ステロイド外用薬、エキシマライトなどの光線療法、ステロイド内服薬、外科手術などがあります。かゆみや痛みなどの自覚症状がないため、すぐに気付かないこともありますが、発症部位によっては日常生活や生活の質(QOL)に影響を及ぼすこともあるため、症状が現れた場合は早めに適切な診断と治療を受けることが重要です。
酒さ(赤ら顔)
酒さは、主に鼻から頬を中心にした顔面に、ほてりや発赤、ニキビのような発疹、ヒリヒリとした症状が現れる皮膚疾患です。中高年の女性に多く見られ、肌質は敏感肌と脂性肌(オイリー肌)のいずれでも起こるとされています。酒さの原因や明確なきっかけは不明確ですが、紫外線や気温の変化、アルコール、カフェイン、香辛料などの刺激のある食品、または皮膚の擦れによる外的刺激が原因とされています。根本的な治療法は確立されていないため、現状を悪化させない、維持するための治療が中心となります。
掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)
掌蹠膿疱症とは、手の平や足の裏に小さな膿の袋(膿疱)や水ぶくれが現れ、良くなったり悪くなったりを繰り返す疾患です。膿疱や水泡だけでなく、発赤、ひび割れ、爪の変形などの症状を伴うこともあります。 この疾患の発症には、喫煙、扁桃炎、歯周病、金属アレルギーなどが関与しているとされています。 症状に応じて、ビタミンD3外用薬やステロイド外用薬などを中心に治療を行っていきます。
多汗症
多汗症は通常の汗とは異なり、特に暑いわけでも運動したわけでもないのに過剰に汗が出て、日常生活に支障をきたす状態です。多汗症は手や脇に限局して発生する「局所性多汗症」と、全身にわたって汗が大量に出る「全身性多汗症」があります。局所性多汗症には外用薬を使用し、全身性多汗症には内服治療を中心に治療を行います。小学生から使用可能な保険適用の薬もあります。 多汗症とワキガを混同される方もいらっしゃいますが、ワキガ(腋臭症)は、腋や外陰部などにあるアポクリン腺から分泌されるネバネバした汗と、皮膚上の細菌の影響によって特有の臭いが発生するものです。ワキガは遺伝的な要因が関与することがあり、日本人の約10%がワキガであるとされています。ワキガの治療として、保険診療と自費診療があり、保険診療では外用薬、自費診療ではボトックス注射などを行います。